スーパーに行ったものの、買おうと思っていた商品を忘れてしまう。家に戻ってから必要な物を思い出し、再度買い物に行く羽目になる、家事の途中で次にすることを決めていたけど何だったか思い出せない忙しい日々が続きますね。
「隙間時間」や「ながら読書」も活用して、読書は手放したくないですね。
結論 記憶力の定着には法則があるっぽい
記憶力の低下や忘れっぽさは、日々の生活習慣を少し変えるだけで改善できるそうです。
- 十分な睡眠
- 規則正しい運動
- バランスの良い食事
- 人との交流
- 新しいことへの挑戦
- 瞑想やリラックスの時間を作る
- 定期的な脳トレ
次の本を読んで、記憶力の低下や忘れっぽさに対する対策を学びました。
- ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 脳 久保 健一郎 (監修)ニ
- LIFESPAN(ライフスパン)―老いなき世界 デビッド・A・シンクレア (著)、マシュー・D・ラプラント (著)、梶山 あゆみ (翻訳)の
記憶力の低下と忘れっぽさの原因
まず、記憶力の低下や忘れっぽさの原因について理解することが大切です。
脳の仕組みと記憶の定着
本を読んで驚いたのは、「記憶というのは忘れていくモノですので時間の経過とともに忘却し、復習を繰り返すことによって記憶は定着する」という脳の仕組みです。
つまり、忘れることは自然なプロセスで、むしろ大切なのは記憶を定着させる方法を知ることなのです。
生活習慣と脳の健康
また、「人とあまり関わらない、運動不足、睡眠不足が脳に悪い生活習慣であり、脳の老化や認知機能の低下の大きな原因」であることも分かりました。
これは、私たちの日常生活とも深く関わっています。
記憶力を改善する7つの習慣
では、具体的にどのような習慣を身につければ良いのでしょうか。本から学んだ7つの習慣をご紹介します。
①十分な睡眠をとる
睡眠は記憶の定着に非常に重要です。
特に新しいことを学んだ後は、特に十分な睡眠をとることが大切です。
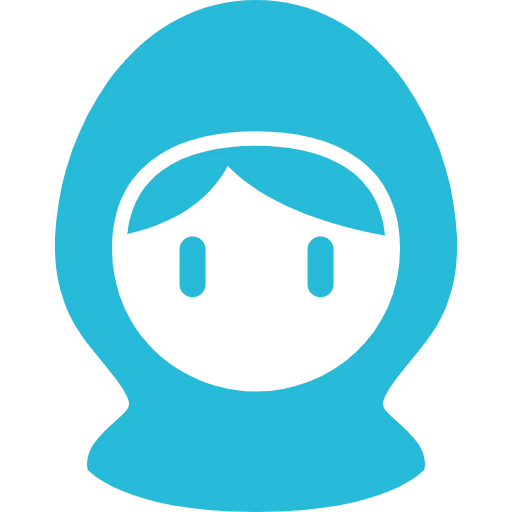
記憶の定着には睡眠
私は、寝る前に30分ほど本を読むようにしています。そうすることで、その日に学んだことが脳に定着しやすくなるそうです。
②運動習慣をつける
運動は脳の血流を良くし、記憶力の向上に役立ちます。
毎日30分程度の散歩や、週に2-3回の軽い運動やストレッチでも大丈夫みたいです。
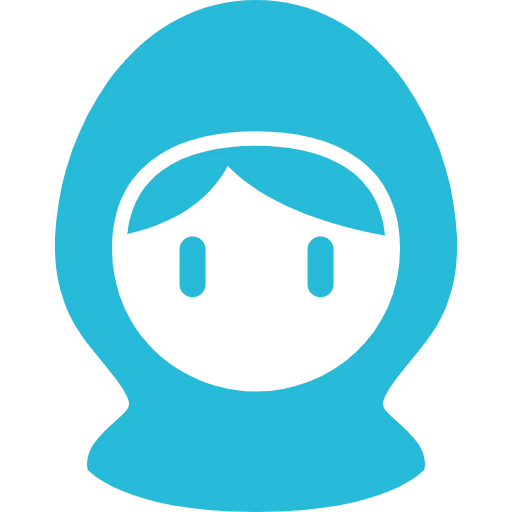
散歩や階段の利用
私は、食材の買い物を兼ねて散歩し、エレベーターやエスカレーターではなく階段を利用するようにしました。
③バランスの良い食事を心がける
脳に良い食事も記憶力の改善に効果があります。
特に、オメガ3脂肪酸を含む魚や、抗酸化物質が豊富な果物や野菜を積極的に摂るようにしましょう。
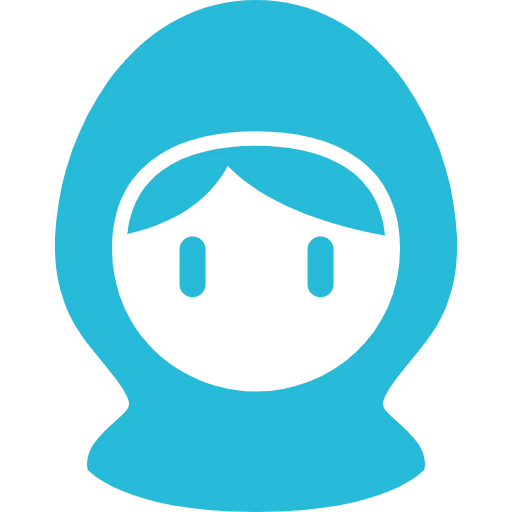
魚と野菜がやっぱり重要でした
私は、週に2-3回は魚料理を取り入れ、夕食には必ず多めにサラダを食べるようにしました。
④人との交流を大切にする
人と会話をすることは、脳を活性化させる良い刺激になります。友人とのおしゃべりや、家族との団らんの時間を大切にしましょう。
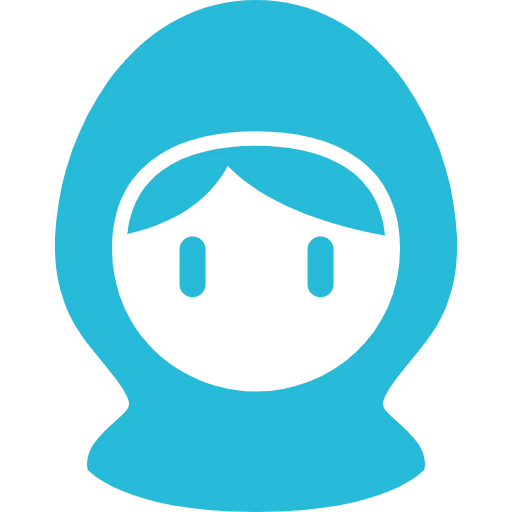
コミュニケーション
私は、家族との食事での会話を意識的に増やし、月に1回は友達とお茶会をする時間を作るようにしています。
⑤新しいことに挑戦する
脳に新しい刺激を与えることも大切です。
趣味を始めたり、新しい言語を学んだりするのも良いでしょう。
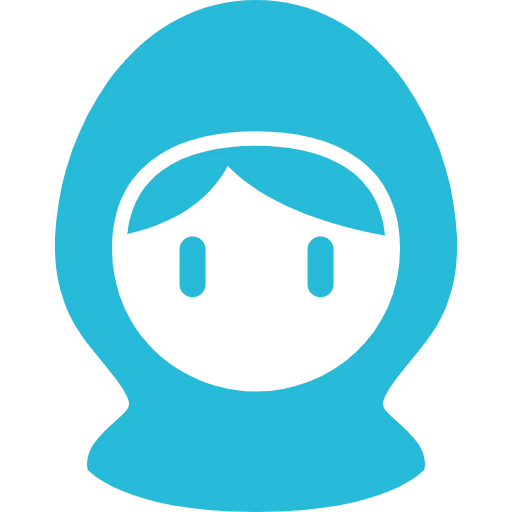
チャレンジ
私は、英会話の勉強をはじめました。
⑥瞑想やリラックスの時間を作る
ストレスは記憶力を低下させる原因の一つです。
瞑想やヨガなどでリラックスする時間を作りましょう。
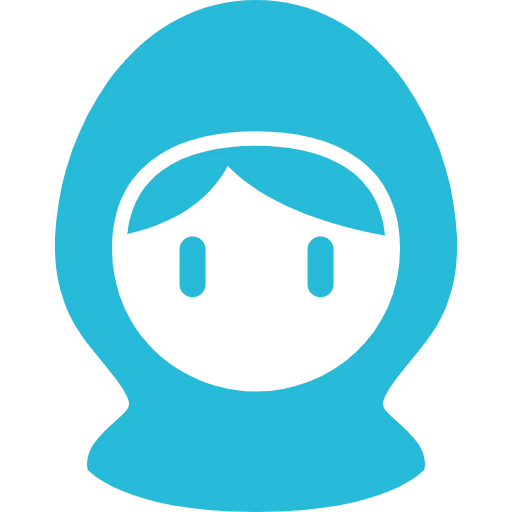
ゆとり
私は、10分早く起きるようにして、その時間でストレッチと深呼吸するようにしました。
⑦定期的に脳トレをする
クロスワードパズルや数独など、脳を使うゲームも記憶力の向上に効果があります。
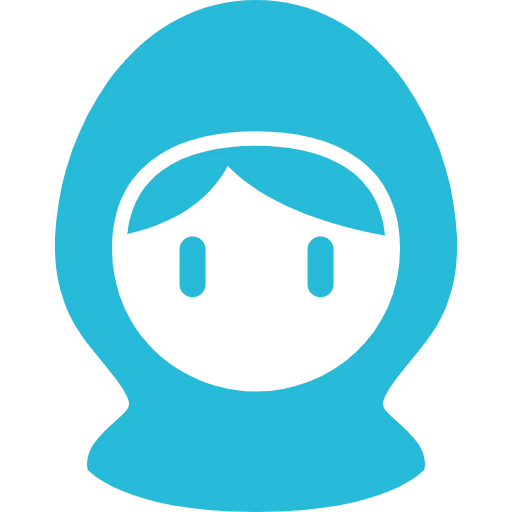
すきま時間
私は、トイレ時の脳トレアプリを日課にしました。
老化への準備と記憶力の維持
記憶力の低下は、老化の一つの兆候でもあります。しかし、「LIFESPAN(ライフスパン)」の著者が提唱するように、私たちは老化に対して積極的に準備することができます。
老化のメカニズムを理解する
本書では、老化は避けられないものではなく、むしろ「治療可能な病気」として捉えられています。
この考え方は、私たちに希望を与えてくれます。
日々の習慣が老化に与える影響
先ほど紹介した7つの習慣は、単に記憶力を改善するだけでなく、老化のプロセスそのものを遅らせる効果があるのです。
科学的なアプローチで老化に立ち向かう
著者は、ある物質が老化に深く関わっていることを発見しました。
この知見を基に、私たちも科学的な視点で老化に向き合うことができます。
記憶力改善の実践例
私自身が実践している記憶力改善の具体例をいくつか紹介します。
買い物リストの工夫
以前は、買い物に行って必要なものを忘れることがよくありました。今は、スマホのメモアプリを使って買い物リストを作り、さらに声に出して読み上げるようにしています。これにより、視覚と聴覚の両方で記憶を強化できます。
名前を覚える技術
人の名前を覚えるのが苦手でしたが、名前を聞いたらすぐにその人の特徴と結びつけるようにしています。
例えば、「山本さん」なら「やまのように背の高い山本さん」というように。これで、名前を思い出すきっかけが増えました。
家事の効率化と記憶力アップ
家事をしながら、頭の中で計算問題を解いたり、英単語を復習したりしています。これにより、単調な作業も脳トレの機会に変えることができます。
食事の工夫
記憶力に良いとされる食材を意識的に取り入れるようにしています。例えばナッツ類、緑茶などです。家族の健康にも良いので一石二鳥です。
記憶力低下への不安を克服する
記憶力の低下は多くの人が経験することですが、それに対する不安や焦りが逆効果になることもあります。
ポジティブな姿勢を保つ
記憶力の改善は、決して難しいことではありません。
日々の小さな努力の積み重ねが大切です。
自分の変化を前向きに捉えることで、モチベーションも維持できます。
周囲のサポートを得る
家族や友人に自分の目標を伝え、協力してもらうのも良いでしょう。
一緒に脳トレゲームをしたり、新しい趣味に挑戦したりするのも楽しいですよ。
専門家のアドバイスを受ける
気になる症状がある場合は、躊躇せずに医療機関を受診しましょう。
早期発見・早期対応が大切です。
記憶力改善がもたらす生活の変化
記憶力が改善すると、日常生活にどのような変化が現れるでしょうか。
自信の回復
物忘れが減ると思えることで、日常生活に自信が持てるようになります。
私自身、買い物で忘れ物をしても、鍛えることで持ち直せると思えるようになり、とても気分が楽になりました。
人間関係の改善
人の名前や約束を忘れにくくなることで、周囲との関係もスムーズになります。
忘れてしまっても、覚えようと工夫している誠意は相手に伝わるものです。
新しい挑戦への意欲
脳の老化にも効果があるとわかると、新しいことへの挑戦も怖くなくなります。
仕事や家事の効率アップ
To-Doリストを頭に入れやすくなり、仕事や家事の効率も上がります。
時間の余裕ができて、自分の趣味の時間も増えるでしょう。
家族との時間の質の向上
家族の予定や記念日を忘れにくくなることで、大切な時間を逃さずに過ごせるようになります。家族との会話も増え、関係がより深まるでしょう。
同じルートを通ることによって自然と山道が出来上がり、その道が太くなっていくように、記憶も何度も何度も繰り返すことによって短期記憶というワーキングメモリーから脳のシナプス間の伝達物質の受け渡しが強い長期記憶に変化してくれるそうなのです。
更には、ものすごいエネルギーを使っている脳は睡眠で休んでいる時に記憶が定着しやすいみたいなのでテストの前日、朝まで寝ないで一夜漬け勉強してもダメなんですね。脳に入れた鮮度を保つために、学習した後にスマホをいじったり、本を読んだりせず、学習直後に寝た方が良いとのことなのです。記憶させたいことは寝る前に学習するようにしないとダメだったのですね。
まとめ:記憶力改善は誰にでもできる
記憶力の低下や忘れっぽさへの対策について、最後に、もう一度重要なポイントをまとめておきます。
- 十分な睡眠
- 規則正しい運動
- バランスの良い食事
- 人との交流
- 新しいことへの挑戦
- 瞑想やリラックスの時間を作る
- 定期的な脳トレ
参考 ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 脳
より詳しく仕組みを把握したい方は ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 脳を読んでみてください。
久保 健一郎 (監修)
私たちは,日常生活で何をするにも「,脳」を使っています。ものを考えたり記憶したりするのはもちろんのこと,うれしい気持ちを感じるのも,体を動かすのだって,脳のはたらきのおかげなのです。脳は,私たちらしさを生む,人体の最重要パーツだといえるでしょう。
脳のはたらきをつくりだしているのは,情報をやりとりする細胞である「神経細胞」です。私たちの脳には,なんと1000億個もの神経細胞があります。脳の中では,それぞれの神経細胞がつながりあって,とても大きなネットワークをつくっています。そして,私たちがものを覚えたり勉強したりするときには,この神経細胞のネットワークに変化がおきることで記憶がつくられると考えられています。
本書は,いまだ多くの謎が残る脳のしくみを“,最強に”面白く紹介する1冊です。本書を読めば,私たちの脳がどれほどすごいのか,きっと実感できることでしょう。ぜひご一読ください!《目次》
イントロダクション
多くの謎に包まれた人体最後の秘境「脳」
脳の中をくわしく見てみよう!
大脳は,場所によってさまざまな役割をもっている
右脳と左脳は,得意分野がちがう
コラム 博士! 教えて!! 脳が大きいほど頭がいいの?1.脳の主役は神経細胞
脳の中には, 1000億個の神経細胞がある
脳の信号は,電線を通って伝えられる
神経細胞どうしは,すきまでへだてられている
脳には,複雑なネットワークがはりめぐらされている
神経細胞には,介護役がいる
コラム もしかしておいしい? 「脳料理」2.謎に満ちた記憶のしくみ
記憶には,さまざまな種類がある
海馬がなくなると,記憶できなくなる
記憶には,神経細胞の変化が必要
受容体がふえて,短期の記憶がつくられる
長期的な記憶には,遺伝子のはたらきが必要
小さな出っぱりがふえて,記憶を形成
コラム 魚を食べると頭はよくなる?
遺伝子を操作して,天才マウス誕生!
おいしい食事は,記憶に残りやすい
学習した直後に眠ると,記憶が定着しやすくなるかも
サルに学習させると脳が膨張した!
海馬の一部が大きいタクシードライバー
コラム 脳の神経細胞はふえないの?
4コマ 医学の祖 ヒポクラテス
4コマ 脳についての重大発見3.感情は脳で生まれる
恐怖の感情を読み取るのに扁桃体が影響している
扁桃体は,さまざまな感情に反応する
喜びや楽しさは,脳の側坐核でつくられる
感情には,古い脳が欠かせない
泣くことで悲しい感情が生まれる
鉄の棒が脳に刺さって,乱暴になったゲージ氏
他人への共感にかかわるミラーニューロン
コラム プラナリアの記憶
4コマ ゴルジとカハール
4コマ 数十年間の大論争4.体の動きも脳しだい
超一流サッカー選手の脳は,活発にはたらいている
大脳基底核の異常で,気をつけができなくなる
バッティングの微調整は,小脳が行う
凡打を重ねて,脳は学習する
脳からの指令は,脊髄を通って筋肉に至る
コラム 電気刺激で「脳ドーピング」5.おそろしい脳の病気
ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 脳
アルツハイマー病
アルツハイマー病は, 40代から忍びよってくる
脳のゴミがアルツハイマー病の原因
掃除係が神経細胞を死に至らせる
アルツハイマー病を完治させる薬はまだない
コラム 博士! 教えて!! 驚異の能力をもつサヴァン症候群
脳卒中
血管が破れたり,詰まったりして,脳卒中がおきる
脳血管の時限爆弾の破裂を未然に防ぐ
血管が詰まったら8時間までが勝負
脳を支配する寄生生物
うつ病
気分障害の患者が, 24年間で11倍に増加
うつ病患者の海馬は,縮小することがある
信号の伝達を改善するうつ病の治療薬
4コマ 脳の地図を作成
4コマ 未完成の脳地図
参考 LIFESPAN(ライフスパン)―老いなき世界
老化こそが病気らしいのですが、老化を治す行動がLIFESPAN(ライフスパン)―老いなき世界で紹介されています。より詳しくは本書を手にとってご確認し、老化を治すアクションを実行されることをオススメします。
★世界20ヵ国で刊行!
★ニューヨーク・タイムズ・ベストセラー!【人類が迎える衝撃の未来!】
人生100年時代とも言われるように、人類はかつてないほど長生きするようになった。
だが、より良く生きるようになったかといえば、そうとはいえない。
私たちは不自由な体を抱え、さまざまな病気に苦しめられながら晩年を過ごし、死んでいく。だが、もし若く健康でいられる時期を長くできたらどうだろうか?
いくつになっても、若い体や心のままで生きることができて、刻々と過ぎる時間を気に病まずに、何度でも再挑戦できるとしたら、あなたの人生はどう変わるだろうか?ハーバード大学医学大学院で遺伝学の教授を務め、長寿研究の第一人者である著者は、そのような世界がすぐそこまで迫っていることを示す。
本書で著者は、なぜ老化という現象が生物に備わったのかを、「老化の情報理論」で説明し、なぜ、どのようにして老化を治療すべきなのかを、最先端の科学的知見をもとに鮮やかに提示してみせる。
私たちは寿命を延ばすとともに、元気でいられる期間を長くすることもできる。
老化遺伝子が存在しないように、老化は避けて通れないと定めた生物学の法則など存在しないのだ。
生活習慣を変えることで長寿遺伝子を働かせたり、長寿効果をもたらす薬を摂取することで老化を遅らせ、さらには山中伸弥教授が突き止めた老化のリセット・スイッチを利用して、若返ることさえも可能となるだろう。では、健康寿命が延びた世界を、私たちはどう生きるべきなのだろうか?
著者によれば、寿命が延びても、人口は急激に増加しない。また、人口が増加しても、科学技術の発達によって、人類は地球環境を破壊せずに、さらなる発展を目指すことができるという。いつまでも若く健康で生きられれば、年齢という壁は消えてなくなる。
孫の孫にも会える時代となれば、私たちは次の世代により責任を感じることになる。変えられない未来などない。
私たちは今、革命(レボリューション)の幕開けだけでなく、人類の新たな進化(エボリューション)の始まりを目撃しようとしているのだ。■世界を代表する知識人が称賛!
「鋭い洞察に満ちた刺激的な書だ。広く深く読まれるべき傑作といえる」
――シッダールタ・ムカジー(科学者。ピュリッツァー賞受賞作家。『遺伝子――親密なる人類史』、『がん――4000年の歴史』著者)「知的好奇心を掻き立ててやまない一冊。じつに興味深い洞察を提供してくれる」
――アンドリュー・スコット(ロンドン・ビジネススクールの経済学教授、『LIFE SHIFT(ライフシフト)――100年時代の人生戦略』著者)【主な内容】
はじめに――いつまでも若々しくありたいという願い第1部 私たちは何を知っているのか(過去)
第1章 老化の唯一の原因――原初のサバイバル回路
第2章 弾き方を忘れたピアニスト
第3章 万人を蝕(むしば)む見えざる病気第2部 私たちは何を学びつつあるのか(現在)
第4章 あなたの長寿遺伝子を今すぐ働かせる方法
第5章 老化を治療する薬
第6章 若く健康な未来への躍進
第7章 医療におけるイノベーション第3部 私たちはどこへ行くのか(未来)
第8章 未来の世界はこうなる
第9章 私たちが築くべき未来おわりに――世界を変える勇気をもとう
謝辞
LIFESPAN(ライフスパン)―老いなき世界
原註
シンクレアの利害関係情報開示
大きさの比較
登場人物紹介
用語集
用語一覧


